「ADHD(注意欠如・多動症)だとシステムエンジニア(SE)には向いていないって本当?」
ネット検索や周囲の声から、そんな不安を感じていませんか?
確かに、SEの業務にはマルチタスクや緻密なコミュニケーションが求められ、ADHDの特性とぶつかりやすい側面もあります。しかし、「向いていない」と諦めるのはまだ早いかもしれません。
この記事では、ADHDを持つ方がSE業務で直面しやすい具体的な課題から、逆に強みとなり得る意外な可能性、そして困難を乗り越えるための実践的な対策、さらには「チームシャイニー」のような専門的な就労移行支援の活用法、SE以外のITキャリアパスまで、多角的に深掘りしていきます。
あなたの特性を活かせる道筋を一緒に探しましょう。
ADHDの特性とシステムエンジニア業務:なぜ「向いていない」と感じやすいのか?

「ADHD(注意欠如・多動症)の自分には、システムエンジニア(SE)は向いていないのかもしれない…」そう感じてしまう背景には、SEという仕事が持つ特有の要求と、ADHDの特性との間に、 leider (残念ながら)ミスマッチが起こりやすい側面があるからです。
決して能力の問題ではなく、特性と業務内容のかみ合わせが難しい場面がある、ということです。具体的にどのような点が課題となりうるのか、一つずつ見ていきましょう。
高度なコミュニケーション能力とマルチタスク遂行の壁
システムエンジニアの重要な役割の一つに、クライアントやチームメンバーとの円滑な意思疎通があります。クライアントが本当に求めていることを引き出すヒアリング能力、複雑な技術要件を分かりやすく説明する能力、多様な関係者(プログラマー、デザイナー、営業など)との調整能力は不可欠です。
しかし、ADHDの特性として、「相手の話を最後まで注意深く聞く」「複数の情報を整理して、論理的に説明する」といった点に苦手意識を持つ方がいます。これが、意図せず誤解を生んだり、プロジェクトの進行に影響を与えたりする可能性が指摘されています。
同時に、SEは複数のプロジェクトやタスクを同時並行で管理し、刻々と変化する状況に合わせて優先順位を判断し、計画的に実行していく能力(マルチタスク能力)を強く求められます。ADHDの実行機能(計画、整理、時間管理など)の特性から、「複数の作業を同時にこなす」「計画通りに進める」「納期を意識してペース配分する」といったことに困難を感じやすい傾向があります。
タスクの切り替え(コンテキストスイッチング)が多いSEの業務は、混乱や疲労を招きやすいとも言われています。
「あれもこれもやらなくては」と焦るばかりで、どれも中途半端になってしまう、という経験を持つ方もいるかもしれません。
緻密さと正確性が求められる作業とケアレスミスの懸念
システム開発の現場では、設計書の記述、プログラミング、テスト仕様書の作成・実行など、細部にわたる正確性と緻密さが要求される場面が数多く存在します。
ADHDの「不注意」特性は、こうした場面でケアレスミス(例:変数名のスペルミス、記号の入力漏れ、設定値の間違い、テスト項目の見落としなど)を引き起こす可能性があります。
ほんの小さなミスが、システム全体の予期せぬ動作や重大な障害につながりかねないため、この点はSEにとって大きなプレッシャーとなりえます。また、長文の仕様書を読み込んだり、詳細なレビューを行ったりする際に、集中力を維持し続けることが難しいと感じることもあります。
興味の波とルーティンワークへのモチベーション維持
ADHDの特性として、自身の興味や関心の度合いによって、集中力やモチベーションが大きく変動することが知られています。
SEの業務には、常に創造的で刺激的なタスクばかりではなく、地道なドキュメント作成、単体テストの繰り返し、定型的な報告書の作成といった、いわゆるルーティンワークも多く含まれます。
こうした、自身の知的好奇心を刺激しにくい作業に対して、意欲を維持し、継続的に取り組むことに困難を感じる場合があります。特に、成果がすぐには目に見えにくい要件定義や基本設計といった上流工程は、達成感を得にくいと感じるかもしれません。
逆転の発想:ADHDの特性はシステムエンジニアリングの「強み」にもなり得る!

しかし、ADHDの特性は決して弱点ばかりではありません。特定の状況や業務内容、そして何より本人の関心と合致したとき、他の人にはないユニークな「強み」として、システムエンジニアリングの世界で輝く可能性を秘めています。
「自分には向いていない」と結論づける前に、ポジティブな側面にも目を向けてみましょう。
「過集中(ハイパーフォーカス)」:驚異的な生産性を生む没入力
ADHDの代表的な特性の一つである「過集中」は、特定の対象に深く没入し、驚異的な集中力を発揮する状態です。
これが、プログラミング(コーディング)、難解なバグの原因特定、複雑なアルゴリズムの理解、新しいプログラミング言語やフレームワークの短期集中学習といった場面で、絶大なパワーを発揮します。
周囲の音も気にならなくなるほどの集中力で、他の人が数日かかるようなタスクを一日で完了させる、といった事例も聞かれます。この「ゾーン」に入る感覚は、多くのADHD当事者エンジニアにとって、仕事のやりがいにも繋がっています。
独創的な「拡散的思考」:イノベーションの起爆剤
ADHDを持つ人は、既存の枠組みや常識にとらわれず、多角的な視点から物事を考え、ユニークなアイデアを生み出す「拡散的思考」が得意な傾向があると言われています。
この能力は、革新的なシステムアーキテクチャの設計、クライアント自身も気づいていない潜在的なニーズの発見、既存システムのボトルネックを解消する斬新なアプローチの提案、直感的で使いやすいユーザーインターフェース(UI)の発想などに活かされます。定型業務よりも、ゼロからイチを生み出すような創造性が求められる場面で、その真価を発揮するでしょう。
好奇心と行動力:変化を恐れない推進力
旺盛な好奇心と、興味を持ったことに対してすぐに行動を起こすフットワークの軽さも、ADHDの特性として挙げられます。技術のトレンドが目まぐるしく変化するIT業界において、新しい技術やツールに対するアンテナの高さと、それを積極的に試してみる行動力は、非常に大きな武器となります。
変化を恐れず、むしろ楽しむことができる姿勢は、プロジェクトに新しい風を吹き込み、チーム全体の推進力となる可能性を秘めています。
「ADHDだからシステムエンジニアは向いていない」ではない!乗り越えるための具体的な対策と工夫

ADHDの特性による困難さを感じていても、諦める必要はありません。
適切な戦略と工夫、そして必要なサポートを得ることで、システムエンジニアとして、あるいはITプロフェッショナルとして活躍する道は開けます。ここでは、今日から試せる個人の工夫と、職場に求めることができる配慮について具体的に解説します。
個人の工夫:自分に合った「外部脳」を作り、実行機能を補う
ADHDの困難さは、脳の実行機能(計画、整理、記憶、自己制御など)の特性に起因することが多いと言われています。意志力だけで乗り切ろうとするのではなく、ツールや環境を「外部脳」として活用し、苦手な部分を補う工夫が非常に有効です。
タスク・時間管理の「見える化」と「細分化」
- タスク分解: 大きな仕事(例:「〇〇機能の設計」)を、「△△画面のレイアウト案作成」「□□処理のフローチャート作成」のように、具体的で実行可能な小さなステップに分解します。これにより、「何から手をつければいいか分からない」状態を防ぎます。
- 視覚的ツール活用: ToDoリスト、カンバンボード(Trelloは視覚的で直感的に使いやすい)、ガントチャート(プロジェクト全体の流れを把握)などを活用し、「やるべきこと」「進捗状況」を常に目に見える形にします。
- 時間管理術: タイムブロッキング(カレンダーに「〇時~〇時:設計作業」と予定を入れる)、ポモドーロテクニック(例:25分集中+5分休憩)、タイマーやアラームの活用で、時間の感覚を補います。リマインダーアプリ(リマインくん、Google Keepなど)で、締め切りや予定を忘れないようにします。
整理整頓のシステム化
- 物理的環境: デスク周りは「物の住所」を決め、使ったら必ず戻すルールを徹底します。書類はファイルボックスやラベルを活用して分類します。
- デジタル環境: ファイル命名規則を決める、フォルダ構成を工夫する、クラウドストレージ(Google Drive, Dropbox)や情報整理ツール(Notionは自由度が高く、様々な情報を一元管理しやすい)を活用して、情報を探しやすく整理します。定期的な整理時間をスケジュールに組み込むのも有効です。
集中力を維持・管理する工夫
- 刺激コントロール: ノイズキャンセリングイヤホンや耳栓、環境音アプリ(カフェの音など)を活用して、周囲の騒音を遮断・調整します。視覚的なノイズ(散らかったデスク、不要なウィンドウ)も減らします。PCやスマホの通知は、集中したい時間はオフにする設定を活用しましょう。
- 作業環境: 可能であれば、パーテーションのある席や個室など、物理的に区切られた空間で作業する、あるいはリモートワークで自宅の集中できる環境を整えることも有効です。
- 能動的な工夫: 集中が途切れたと感じたら、短時間の休憩(5分程度の散歩やストレッチ)を意識的に取る。タスクにゲーム要素を取り入れたり(例:〇個バグを潰したら休憩)、自分の興味と関連付けたりする工夫も効果的です。
記憶・抜け漏れ防止策
- メモの徹底: 会議中、指示受け時、アイデアが浮かんだ時など、どんな些細なことでもメモを取る習慣をつけます。デジタルメモ(Evernote, OneNote)、手書きメモ(常に持ち歩く)、音声入力などを使い分けます。
- 確認の習慣化: 指示を受けたら、自分の理解が正しいか必ず復唱して確認します。作業完了後には、チェックリストを使って抜け漏れがないか確認するプロセスを設けます。
心身のセルフケア
- 睡眠・食事・運動: これらは脳機能の土台です。質の高い睡眠、バランスの取れた食事、定期的な運動(軽い散歩でもOK)は、集中力、衝動性、感情のコントロールに不可欠です。自身の心身の状態をモニタリングする習慣も大切です。
職場での合理的配慮:働きやすい環境を共に創る
物理的環境の調整
- 座席: 騒音や人の往来が少ない静かな場所、壁際や窓際、パーテーションで区切られたスペースなどを希望する。
- 備品: ノイズキャンセリングイヤホンやヘッドホンの業務中の使用許可、必要であれば照明の調整(明るすぎる、チカチカするなど)。
コミュニケーション方法の工夫
- 指示: 口頭だけでなく、メールやチャットなど文字情報での補足を依頼する。「あれ」「それ」といった曖昧な指示を避け、具体的で明確な指示(5W1Hを意識)を依頼する。タスクは一度に一つずつ指示してもらう(シングルタスク)。
- 会議: 事前にアジェンダ(議題、目的、時間配分)を共有してもらう。長時間の会議は休憩を挟むか、短く区切ってもらう。会議の内容は議事録として文字で共有してもらう。
業務の進め方・管理の調整
- タスク管理: 優先順位付けについて相談に乗ってもらう、あるいは明確に指示してもらう。マルチタスクになりすぎないよう、担当するプロジェクトやタスク量を調整してもらう。
- 進捗確認: 定期的な1on1ミーティングなどで、進捗状況の確認や困りごとを相談する機会を設ける。
- チェック体制: 特にミスが許されない重要な作業(例:本番環境へのリリース作業、顧客向け重要書類作成)については、ダブルチェックやレビューの体制を依頼する。
柔軟な働き方の活用
- 勤務時間: フレックスタイム制度を活用し、集中しやすい時間帯にコア業務を行う。
- 勤務場所: リモートワーク(在宅勤務)を可能にする。通勤による疲労やオフィス環境の刺激を避けられるメリットがあります。
これらの配慮を効果的に得るためには、まず自身の特性(何が得意で、何が苦手で、どのような配慮があれば働きやすいか)を整理し、それを上司や人事担当者に具体的に、かつ建設的に伝える「セルフ・アドボカシー(自己権利擁護)」のスキルが重要になります。
後述する就労移行支援などでは、この伝え方の練習や、企業への説明資料作成のサポートも行っています。
ADHDシステムエンジニアは向いていない?就労移行支援とは?:総合的なサポート

就労移行支援は、一般企業等への就職を目指す、障害や難病のある方を対象とした通所型のサービスです。原則として最長2年間、個別の支援計画に基づき、就職に必要な知識・スキルの向上から、就職活動、そして就職後の職場定着まで、一貫したサポートを提供します。多くの場合、前年の世帯収入に応じて利用料が決まり、約9割の方が自己負担なし(無料)または月額9,300円以下の負担で利用しています。
提供されるサポート内容は事業所によって特色がありますが、一般的には以下のようなものが含まれます。
自己理解プログラム:自分のトリセツ(取扱説明書)を作る
自身のADHD特性(集中力の波、衝動性、得意なこと、苦手なこと、感覚過敏など)を、様々な角度から客観的に見つめ直します。
心理検査やグループワーク、スタッフとの面談を通じて、「なぜ自分はこう感じるのか」「どんな時に力を発揮しやすいか/困難を感じやすいか」を深く理解します。単に弱点を認識するだけでなく、「過集中」や「独創性」といった強みをどう活かすか、具体的な戦略を考えます。
また、ストレスへの対処法(コーピング)、感情のコントロール方法、自身の状態を良好に保つための工夫(WRAP:元気回復行動プランのような考え方を取り入れることも)などを学び、自分だけの「取扱説明書」を作成していくイメージです。これは、後々、職場へ必要な配慮を伝える際にも役立ちます。
ビジネススキル訓練:働く上での土台を固める
社会人として働く上で基本となるスキルを、実践的に学びます。例えば、適切な敬語の使い方、ビジネスメールの書き方、電話応対(必要に応じて)、効果的な報告・連絡・相談(ホウレンソウ)の方法、会議での適切な振る舞いなどを、ロールプレイングなどを通じて習得します。
特にADHDの方が苦手としやすい、時間管理(タスクの優先順位付け、スケジュール管理ツールの活用法)、整理整頓(デスク周り、情報管理)、ストレスマネジメント(感情の波との付き合い方)などについても、具体的な対処法を学び、トレーニングします。
専門スキル訓練:IT分野で活躍するための武器を磨く
目指す職種(SE、プログラマー、Webデザイナー、データアナリストなど)に応じて、実践的な専門スキルを習得します。IT分野に特化した事業所では、プログラミング言語(Python, Java, JavaScript, PHPなど)、データベース(SQL)、ネットワーク、サーバー構築、クラウド技術(AWS, Azure, GCP)、Webデザイン(HTML, CSS, デザインツール)、データ分析ツール(Excel応用, Tableau, Pythonライブラリ)、バージョン管理(Git)、プロジェクト管理ツール(Jira, Backlog)など、幅広いカリキュラムが用意されています。単に知識を詰め込むだけでなく、模擬プロジェクトや課題制作を通じて、実際に「手を動かして作る」経験を積み、ポートフォリオ(自身のスキルを証明する作品集)を作成することも重視されます。
就職活動サポート:自分に合った企業との出会いを支援
キャリアカウンセリングを通じて、自身の希望や特性に合った職種や企業選びをサポートします。ハローワークや転職エージェントと連携し、障害者雇用枠を含む求人情報を提供。応募書類(履歴書、職務経歴書)の作成では、自身の強みや経験、必要な配慮などを効果的に伝えるための添削指導を行います。面接対策では、よく聞かれる質問への回答準備はもちろん、ADHD特性(例:多動で落ち着かない、話が脱線しやすい)を踏まえた上での模擬面接を繰り返し行い、自信を持って臨めるようにサポートします。企業見学や数日~数週間の職場実習(インターンシップ)を通じて、実際の仕事内容や職場の雰囲気を体験する機会も提供されます。
専門スキル訓練:IT分野で活躍するための武器を磨く
目指す職種(SE、プログラマー、Webデザイナー、データアナリストなど)に応じて、実践的な専門スキルを習得します。IT分野に特化した事業所では、プログラミング言語(Python, Java, JavaScript, PHPなど)、データベース(SQL)、ネットワーク、サーバー構築、クラウド技術(AWS, Azure, GCP)、Webデザイン(HTML, CSS, デザインツール)、データ分析ツール(Excel応用, Tableau, Pythonライブラリ)、バージョン管理(Git)、プロジェクト管理ツール(Jira, Backlog)など、幅広いカリキュラムが用意されています。
単に知識を詰め込むだけでなく、模擬プロジェクトや課題制作を通じて、実際に「手を動かして作る」経験を積み、ポートフォリオ(自身のスキルを証明する作品集)を作成することも重視されます。
就職活動サポート:自分に合った企業との出会いを支援
キャリアカウンセリングを通じて、自身の希望や特性に合った職種や企業選びをサポートします。ハローワークや転職エージェントと連携し、障害者雇用枠を含む求人情報を提供。応募書類(履歴書、職務経歴書)の作成では、自身の強みや経験、必要な配慮などを効果的に伝えるための添削指導を行います。
面接対策では、よく聞かれる質問への回答準備はもちろん、ADHD特性(例:多動で落ち着かない、話が脱線しやすい)を踏まえた上での模擬面接を繰り返し行い、自信を持って臨めるようにサポートします。企業見学や数日~数週間の職場実習(インターンシップ)を通じて、実際の仕事内容や職場の雰囲気を体験する機会も提供されます。
職場定着支援:就職後も続く、安心のサポート体制
就職はゴールではなく、スタートです。新しい環境で安定して働き続けるためには、入社後のサポートが非常に重要です。
就労移行支援事業所では、就職後も一定期間(法律では原則6ヶ月、多くの事業所ではそれ以上の期間、あるいは必要に応じて継続的に)、定期的な面談(本人、企業の人事担当者や上司、支援機関スタッフの三者面談など)を実施します。
業務上の悩み、人間関係、体調管理、必要な配慮が適切に得られているかなどを共有し、問題があれば早期に解決策を一緒に考えます。支援スタッフが、本人と企業との間の橋渡し役となり、円滑なコミュニケーションをサポートしてくれるため、一人で抱え込まずに済みます。長期的なキャリアプランの相談にも乗ってくれます。
障害者手帳を持っていなくても、医師の診断書や、「自立支援医療(精神通院)」の受給者証などがあれば、自治体の判断により利用できる場合があります。まずは、お住まいの自治体の障害福祉窓口や、関心のある就労移行支援事業所に相談してみることをお勧めします。
職場定着支援:就職後も続く、安心のサポート体制
就職はゴールではなく、スタートです。新しい環境で安定して働き続けるためには、入社後のサポートが非常に重要です。就労移行支援事業所では、就職後も一定期間(法律では原則6ヶ月、多くの事業所ではそれ以上の期間、あるいは必要に応じて継続的に)、定期的な面談(本人、企業の人事担当者や上司、支援機関スタッフの三者面談など)を実施します。
業務上の悩み、人間関係、体調管理、必要な配慮が適切に得られているかなどを共有し、問題があれば早期に解決策を一緒に考えます。支援スタッフが、本人と企業との間の橋渡し役となり、円滑なコミュニケーションをサポートしてくれるため、一人で抱え込まずに済みます。長期的なキャリアプランの相談にも乗ってくれます。
障害者手帳を持っていなくても、医師の診断書や、「自立支援医療(精神通院)」の受給者証などがあれば、自治体の判断により利用できる場合があります。
まずは、お住まいの自治体の障害福祉窓口や、関心のある就労移行支援事業所に相談してみることをお勧めします。
【注目】先端IT特化型就労移行支援「チームシャイニー」の強み
数ある就労移行支援事業所の中でも、特に先端IT分野に特化し、ADHDなどの発達障害のある方の特性を活かした支援で注目されているのが「チームシャイニー」です。SEやITエンジニアを目指す上で、なぜチームシャイニーが有力な選択肢となりうるのか、その特徴を見てみましょう(出典:AIの就労移行事業所IT特化【チームシャイニー】東京秋葉原千代田区)。
超実践的カリキュラム
AI(機械学習)、データサイエンス、Web開発/マーケティングといった、現代のIT業界で需要の高い分野に特化。Python、SQL、Tableau、AWS、ChatGPT活用など、現場で即使えるスキルを、プロジェクトベースの課題を通じて実践的に学びます。「手を動かしながら学ぶ」「すぐに成果が見える」課題設計は、ADHDの「過集中」を引き出し、学習意欲を高める工夫がされています。
「当事者×専門家」による個別伴走サポート
スタッフは全員が現役のITエンジニアであり、かつ発達障害の当事者でもあります。そのため、技術的な指導の質が高いだけでなく、ADHD特有の悩み(タスク管理が苦手、集中力が続かない、コミュニケーションで誤解されやすい等)に対する深い共感と理解に基づいた、具体的で的確なアドバイス(JiraやNotionを使ったタスク管理術、特性に合ったコミュニケーション方法など)が受けられます。まさに「分かる人」が伴走してくれる安心感があります。
高い就職実績と徹底した定着支援
卒業生の多くが、NTTグループ、大手メーカー、自社開発企業など、優良IT企業へ技術職(プログラマー、データアナリスト、AIエンジニア等)として就職しています(公式サイトに実績多数掲載)。就職活動においては、企業への特性説明や合理的配慮の伝え方を一緒に考え、面接にも同行。さらに、就職後も最長180日間(法定は6ヶ月だが、実質的なサポート期間として強調)にわたる手厚い定着支援で、入社後のギャップ解消や職場への適応を長期的にサポートします。この定着支援の手厚さが、長く働き続ける上で非常に重要です。
特性に配慮された学習環境
東京・秋葉原にあるオフィスは、感覚過敏に配慮し、防音ブースや照度調整可能なライトを設置。静かな環境で集中して学習に取り組めます。また、Zoomなどを活用したフルリモートでの受講にも対応しており、全国どこからでも利用可能です。
経済的負担の軽減
国の制度に基づいているため、利用者の**95%以上が自己負担なし(無料)**で利用しています。経済的な心配なく、スキルアップと就職活動に専念できます。
公的機関からの信頼
総務省「異能vation」ネットワーク拠点認定や東京都ソーシャルファーム認証など、公的な評価・認定も受けており、支援の質の高さと信頼性がうかがえます。
チームシャイニーのような専門機関は、ADHDの特性を「弱み」ではなく「活かすべき個性」と捉え、ITエンジニアとして必要なスキル、自己管理能力、そして自信を育むための最適な環境を提供してくれます。
「SEは向いていないかも…」という不安を、「自分ならできるかも!」という確信に変えるための、具体的な第一歩となるでしょう。無料での個別相談や事業所見学、オンライン説明会も随時実施されているので、まずは気軽に情報を集めてみることを強くお勧めします(連絡先:チームシャイニー公式サイトをご確認ください)。
ADHDシステムエンジニアは向いていない:IT・エンジニアリング分野の多様なキャリアパス
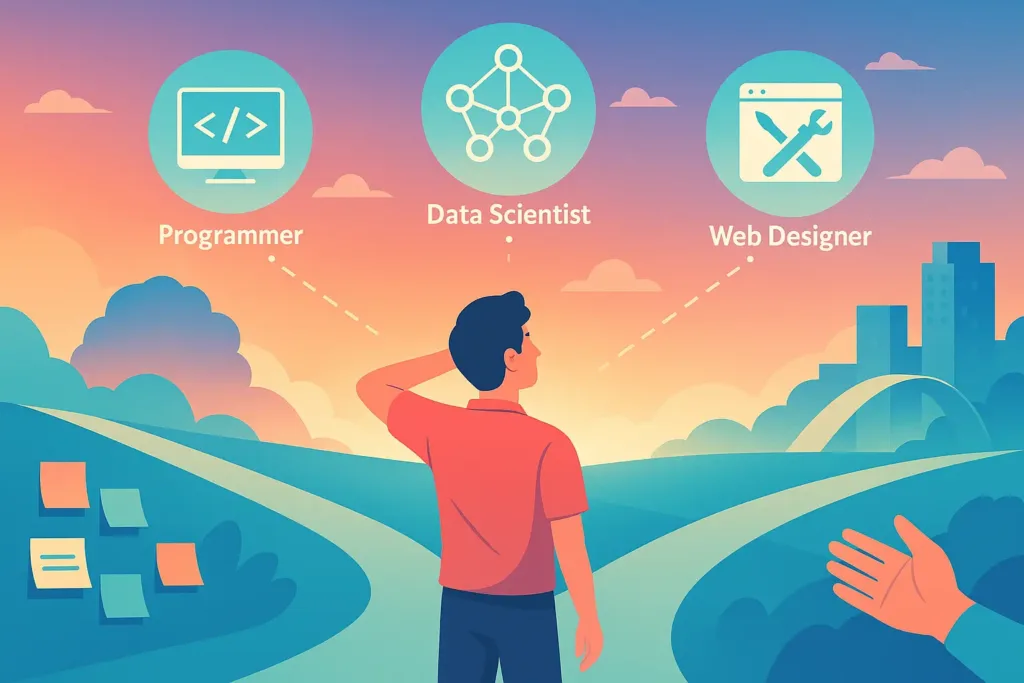
様々な工夫やサポートを試した結果、やはりシステムエンジニア、特に顧客折衝やプロジェクト全体の管理といった業務が中心となる役割は、自分には合わないと感じることもあるかもしれません。
しかし、それでIT業界を諦める必要は全くありません。IT・エンジニアリングの世界は広く、あなたの特性が活きる道は他にもたくさん存在します。
「作る」に集中したいなら:プログラマーやWebデベロッパー
システムエンジニア(SE)と比較して、プログラマー(PG)は、設計書に基づいて実際にコードを書く「実装」の工程に、より多くの時間を費やす傾向があります。顧客との直接的なコミュニケーションや、プロジェクト全体の管理業務の比重がSEよりも少ないことが一般的です。そのため、「人と話すより、黙々とコードを書きたい」「仕様が決まっていれば、集中して作り上げることができる」「過集中をコーディングに活かしたい」というタイプの方には、PGの方が適性が高い可能性があります(出典:kizuki-corp.com, atgp.jp)。WebサイトやWebアプリケーションの制作を専門とするWebデベロッパーも、技術スキルとデザインセンス(あれば尚良し)を活かせる人気の職種です。
特定分野のスペシャリストを目指す道
- データサイエンティスト/アナリスト: 膨大なデータの中から価値ある知見を見つけ出す仕事です。論理的思考力、分析力、そしてデータの中に隠されたパターンを見つけ出す探求心や「過集中」が活きる分野です。統計学やプログラミング(Python, R)、データベースの知識が求められます。
- テストエンジニア/QAエンジニア: 開発されたシステムやソフトウェアの品質を保証する役割です。単にテストを実行するだけでなく、テスト計画の立案、テスト自動化ツールの開発・運用、品質改善提案など、専門性は多岐にわたります。細部への注意力は必要ですが、「バグを見つける」という問題解決の側面や、効率的なテスト手法を探求することに面白さを見いだせるかもしれません。
- インフラエンジニア/クラウドエンジニア: サーバー、ネットワーク、データベースといった、システムが動くための基盤(インフラ)を設計、構築、運用する仕事です。近年はAWS、Azure、GCPといったクラウド技術の専門知識が重要になっています。比較的、対人折衝よりも技術的な専門性が重視される傾向があります。
- セキュリティエンジニア: サイバー攻撃からシステムや情報を守るための対策を専門とする仕事です。常に最新の脅威や技術動向を学び続ける必要があります。
- ITサポート/ヘルプデスク: 社内外のユーザーからの技術的な問い合わせに対応し、問題を解決する仕事です。コミュニケーション能力も必要ですが、困っている人を助けることにやりがいを感じる人に向いています。
- テクニカルライター: 技術的な情報を、マニュアルや仕様書として分かりやすく文書化する専門職です。文章構成力や正確性が求められます。
- その他: ゲーム開発者、UI/UXデザイナー(ユーザーにとって使いやすいデザインを考える)、組み込みエンジニア(家電や自動車などに搭載されるシステムの開発)など、ITが関わる分野は非常に広範です。
キャリアパスを考える上で最も重要なのは、「システムエンジニア」という職種名にとらわれず、「具体的にどのような作業内容に興味があるか」「どのような働き方が自分に合っているか(チーム作業中心か、個人作業中心か、変化が多いか、安定しているかなど)」「自身のADHD特性(特に強み)をどのように活かせそうか」という視点から、多角的に検討することです。
就労移行支援事業所のスタッフや、キャリアカウンセラー、信頼できる当事者の先輩などに相談しながら、自分らしいキャリアの道筋を見つけていくことが大切です。
まとめ:ADHDシステムエンジニアは向いていない
ADHDだからといって、システムエンジニア(SE)という仕事が一律に「向いていない」わけではありません。コミュニケーションの複雑さ、マルチタスク、緻密な管理能力が求められる場面では困難を感じやすい一方、プログラミングや問題解決における「過集中」、既成概念にとらわれない「創造性」は、IT分野で強力な武器となり得ます。
大切なのは、自身のADHD特性(強みと弱み)を深く理解し、具体的な業務内容や職場環境との相性を見極めること。そして、タスク管理ツールの活用や環境調整といった個人的な工夫に加え、「チームシャイニー」のような専門的な就労移行支援機関のサポートを積極的に活用し、必要な合理的配慮を得ながら働く戦略を持つことです。
もしSEという役割がどうしても合わないと感じても、IT業界にはプログラマー、Webデベロッパー、データサイエンティストなど、あなたの特性がより活きる多様なキャリアパスが存在します。この記事が、あなたが自分らしい働き方を見つけるための一助となれば幸いです。「向いていない」という思い込みを手放し、可能性を広げる一歩を踏み出してみませんか。

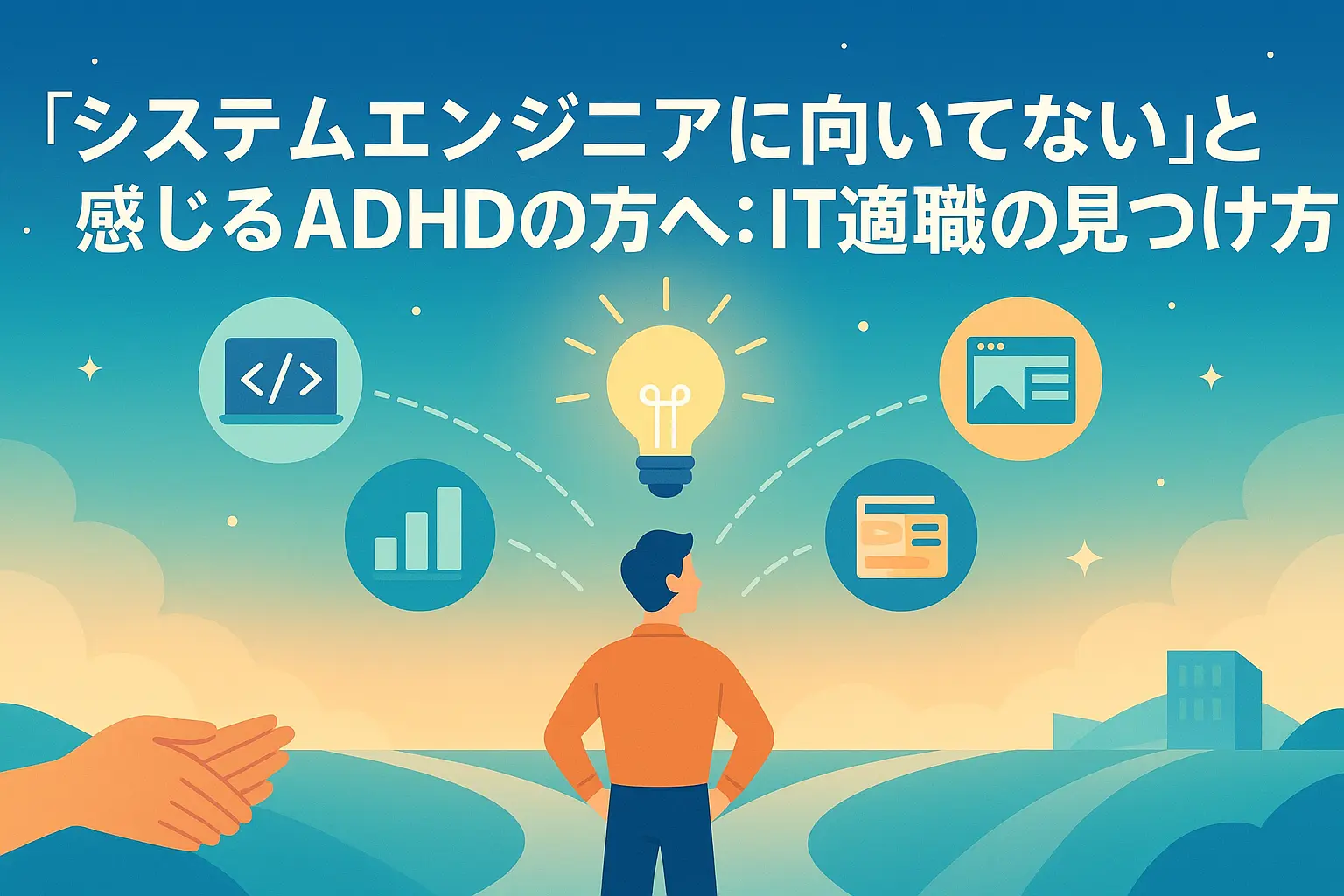

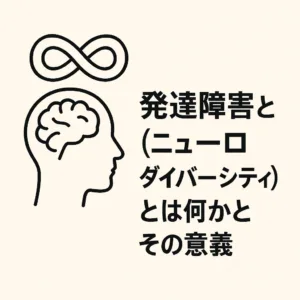
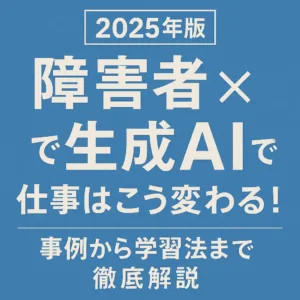
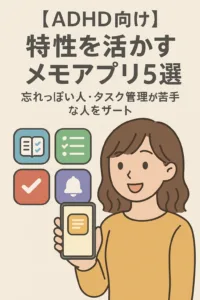

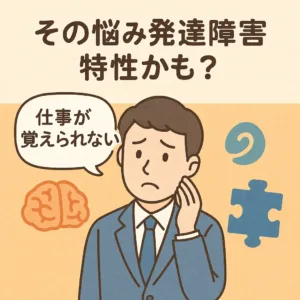
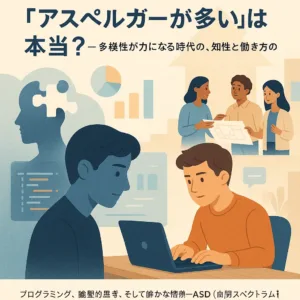

コメント