「自分に合った仕事が見つからない」「ADHDの特性のために業務に困難を感じる」そんな悩みを抱えていませんか?
ADHD(注意欠如・多動症)の特性は、確かに困難をもたらすこともありますが、見方を変えれば、ユニークな強みとして輝きを放つ可能性を秘めています。
この記事では、「ADHDに向いている仕事」をテーマに、あなたの特性を最大限に活かせる職業一覧から、具体的な仕事選びのポイント、職場で実践できる工夫、さらには利用可能な支援制度まで、網羅的に解説します。この記事を読めば、自分らしいキャリアを築くためのヒントが見つかるはずです。あなたの可能性を広げる一歩を、ここから踏み出しましょう。
ADHDの方に向いている仕事一覧

ADHDの特性を活かせる仕事は多岐にわたります。ここでは、一般的にADHDの方に向いているとされる職種を、その理由や具体例とともにご紹介します。
クリエイティブ系の仕事
独創的なアイデアや自由な発想を形にできるクリエイティブ系の仕事は、ADHDの強みである「創造性」や「過集中」を活かしやすい分野です。
向いている理由としては、斬新なアイデアやユニークな視点が求められること、興味のあるプロジェクトに没頭しやすいこと、視覚的な情報を扱う仕事が多く視覚優位の特性を持つ場合に有利であること、個人の裁量で進められる業務が多い場合があることなどが挙げられます。
職種例としては、デザイナー系ではWEBデザイナー、グラフィックデザイナー、UI/UXデザイナー、CGアニメーター、イラストレーター、インテリアデザイナー、ファッションデザイナーなどがあります。
アーティスト系では漫画家、画家、作家、コピーライター、俳優、ミュージシャン、声優、映像クリエイター、写真家、建築家などが考えられます。
特に、WEBデザイナーやイラストレーターなどは、自分のペースで作業を進めやすく、成果物が明確であるため、達成感を得やすいという特徴もあります。
IT・エンジニア系の仕事
論理的思考力や問題解決能力、そして特定の技術への「過集中」を活かせるIT・エンジニア系の仕事も、ADHDの方に適性があると言われています。
向いている理由としては、仕事のゴールや指示が明確で具体的な成果物が求められること、論理的に問題を解決していくプロセスに集中しやすいこと、技術の進歩が速く常に新しい知識やスキルを追求できるため好奇心を満たしやすいこと、リモートワークやフレックスタイム制など柔軟な働き方が可能な企業が多いこと、個人作業が多く対人ストレスが比較的少ない場合があることなどが挙げられます。
職種例としては、ゲームプログラマー、WEBエンジニア、ソフトウェアエンジニア、システムエンジニア(特に下流工程)、ネットワークエンジニア、AIエンジニア、データサイエンティスト、ITコンサルタント、メンテナンスエンジニア、フィールドエンジニアなどがあります。
プログラミングなどは、一度集中すると時間を忘れて没頭できる「過集中」の特性を最大限に活かせる分野の一つです。また、成果物で評価されることが多いため、評価基準が明確な点も魅力です。
高強度・高速ペースの仕事
常に状況が変化し、高いエネルギーレベルと迅速な判断力が求められる仕事は、ADHDの「行動力」や「アドレナリン駆動型の集中力」を活かせる可能性があります。
向いている理由としては、変化が多く単調さを感じにくいこと、瞬間的な判断力や対応力が求められること、高いエネルギーレベルを維持しやすいことなどが挙げられます。
職種例としては、救急医療従事者(救急医、ER看護師、救急救命士)、消防士、警察官、ジャーナリスト、報道カメラマン、イベントプランナー、ツアーコンダクター、一部の教師(特に変化の多い学級や活動的な教科)などがあります。
ただし、これらの職種はミスが許されない場面も多いため、衝動性をコントロールする工夫や、チームとの連携が重要になります。
専門性・興味を追求できる仕事
特定の分野に深い興味を持ち、専門知識やスキルを極めていく仕事は、ADHDの「過集中」や「探求心」を存分に発揮できる分野です。
向いている理由としては、興味のある分野であれば時間を忘れて没頭し高い専門性を身につけられること、自分のペースで研究や作業を進められる場合があること、知的好奇心を満たし続けられることなどが挙げられます。
職種例としては、研究者、学者、大学教員、調理師、パティシエ、自動車整備士、機械エンジニア、スポーツ選手、インストラクター、弁護士、社会福祉士、カウンセラー(特定の専門分野を持つ場合)、職人(伝統工芸、家具製作など)などがあります。
歩合制の営業職なども、成果が直接収入に結びつくため、高いモチベーションを維持しやすく、自分のペースで目標を追求できる点で適性がある場合があります。
起業家・自営業
自分で仕事内容やスケジュールをコントロールできる起業家やフリーランスといった働き方は、ADHDの特性を活かしやすい選択肢の一つです。
向いている理由としては、自分の興味やアイデアを追求し自由に事業を展開できること、働く時間や場所を自分で決められるため集中しやすい環境を作りやすいこと、多様な業務に関わるため飽きにくいこと、行動力や決断力を活かしてスピーディーに事業を進められることなどが挙げられます。
職種例としては、起業家、経営者、フリーランス(ライター、デザイナー、コンサルタント、プログラマーなど)、小規模ビジネスのオーナー(カフェ、雑貨店など)、コンテンツクリエイター(YouTuber、ブロガーなど)などがあります。
ただし、自己管理能力や事務処理能力も求められるため、苦手な部分は外部委託するなどの工夫が必要です。
その他(営業・コミュニケーション系、カウンセリング・福祉系など)
上記以外にも、ADHDの特性を活かせる可能性のある職種はあります。
営業・コミュニケーション系では、営業職(特に新規開拓)、接客業(変化が多い店舗など)、カスタマーサポートなどが考えられます。これらは行動力やコミュニケーション能力、人当たりの良さを活かせ、状況に応じた柔軟な対応が得意な場合に適しています。
カウンセリング・福祉系では、カウンセラー、ソーシャルワーカー、心理士、介護福祉士などが挙げられます。感受性の高さや共感力を活かし、人の役に立ちたいという思いが強い場合に適しており、相手の感情を敏感に察知する能力が役立ちます。
ADHDの方が仕事選びで重視すべきポイント

自分に合った仕事を見つけるためには、以下のポイントを意識することが大切です。
自己理解を深める(自分の特性、強み・弱みを知る)
まず、自分自身のADHDの特性(不注意優勢型、多動・衝動性優勢型、混合型など)や、どのような状況で強みを発揮でき、どのような場面で困難を感じやすいのかを客観的に把握することが重要です。過去に「過集中」できた経験や、心から楽しいと感じた活動を振り返ることも有効です。
働く環境の自由度(フレックス、リモートなど)
勤務時間や場所に柔軟性があるかどうかも重要なポイントです。フレックスタイム制であれば自分の集中しやすい時間帯にコア業務を行え、リモートワークであれば通勤のストレスがなく自宅など自分が最も集中できる環境で働けます。また、裁量労働制は仕事の進め方や時間配分を自分でコントロールしやすいというメリットがあります。自分のペースで仕事を進められる環境は、ADHDの特性を持つ方にとってパフォーマンスを発揮しやすいと言えます。
興味・関心を追求できるか(過集中を活かす)
ADHDの最大の強みの一つである「過集中」を活かすためには、自分が心から興味を持てる分野や内容の仕事を選ぶことが極めて重要です。「好きこそものの上手なれ」という言葉があるように、興味のあることであれば、自然と集中力が高まり、高い成果を上げやすくなります。
刺激レベル・自己裁量・スキルタイプ(3軸フレーム)
仕事を選ぶ際には、以下の3つの軸で職場環境を見極めるのも有効です。
一つ目は刺激レベルです。緊急対応や変化が多いか、それとも定型的で静穏な環境か。ADHDの方は比較的高刺激な環境を好む傾向がありますが、同時に休息を取りやすい制度(例:休憩時間の自由度が高い、仮眠スペースがあるなど)も重要です。
二つ目は自己裁量です。仕事の進め方や方法を自分で決められるか、それとも決まった手順を守る必要があるか。タスク設計の自由度が高いほど、パフォーマンスを伸ばしやすい傾向があります。
三つ目はスキルタイプです。自分の「強みプロファイル」(例:多面的な発想力、ハイパーフォーカス、パターン認知など)に合ったスキル(創造系、分析系、身体を動かす系など)が求められるか。
この3軸をマトリクス化し、自分にとって最適なゾーン(例:高刺激 × 高裁量 × 得意スキル)に入る仕事を狙うのが一つの戦略です。
ADHD仕事の向いているを探す過集中日本で活用できる支援制度・プログラム

ADHDの方が安心して働き、能力を発揮するためには、様々な支援制度やプログラムを活用することも有効です。
障害者雇用枠の活用(メリット・デメリット)
精神障害者保健福祉手帳を取得している場合、障害者雇用枠での就職活動が可能です。厚生労働省の「令和5年障害者雇用状況の集計結果」によると、ADHDを含む精神障害者の雇用は130,298人(前年比18.7%増)と、障害種別で最も増加率が高くなっており、企業の理解も進みつつあります。
メリットとしては、企業に対してADHDの特性への合理的配慮(業務内容の調整、通院への配慮など)を法的に求めることができること、障害への理解がある職場で働ける可能性が高まること、求人によっては一般雇用よりも競争率が低い場合があることなどが挙げられます。
デメリットとしては、一般雇用に比べて求人数が少ない傾向があること、職種や業務内容が限定される場合があること、給与水準が一般雇用よりも低い場合があることなどが考えられます。
一般雇用で働くか、障害者雇用枠で働くかは、ご自身の状況や希望、キャリアプランなどを総合的に考慮して判断することが大切です。
ADHDと共に輝くためのキャリア戦略

ADHDの特性を強みに変え、充実したキャリアを築くためには、戦略的なアプローチが必要です。
強みを活かすためのスキル開発
ADHDの特性を活かすためには、以下の4つのスキルを体系的に身につけることが重要です。
一つ目は自己理解と自己受容です。自分の特性を深く理解し、強みと弱みを客観的に把握します。
二つ目はタスク・時間管理です。外部ツール(アプリ、手帳など)を活用し、効果的なタスク管理と時間管理の習慣を身につけます。
三つ目はコミュニケーションです。職場や対人関係において、自分の考えを適切に伝え、相手の意図を正確に理解する技術を習得します。
四つ目は環境調整です。自分にとって最適な作業環境を構築し、集中力を高めるスキルを身につけます。
これらのスキルは、就労移行支援事業所のトレーニングなどを通じて習得することも可能です。
面接・働き始めのリアル戦略
「開示」か「非開示」かを決めることは重要な戦略の一つです。障害者雇用枠では、勤務時間や作業内容について法的な配慮を求めやすいですが、求人が限定的になる場合があります。一方、一般雇用枠では職種選択の幅が広いですが、配慮は自分で交渉する必要があります。仕事への影響度や、職場の理解度などを考慮して慎重に判断しましょう。
合理的配慮は「提案型」で求めることが効果的です。配慮を求める際は、一方的に要求するのではなく、「こうすればより貢献できます」「このようなサポートがあれば、よりスムーズに業務を行えます」といった形で、企業側にもメリットがあるように提案することが大切です。例えば、「毎朝5分のスタンドアップミーティングでタスクを確認させていただけますか?」「指示は口頭だけでなく、Slackなどのチャットツールにも残していただけると助かります。」「集中力を高めるために、ノイズキャンセリングヘッドフォンの使用許可を経費で購入申請してもよろしいでしょうか?」といった具体的な提案が考えられます。
ジョブクラフティングも有効な戦略です。就業後、自分の得意な業務の割合を増やし、苦手な業務は他の人に任せたり、やり方を工夫したりするなど、主体的に仕事内容を再設計していく視点も重要です。例えば、「就業後3ヶ月以内に得意タスクを20%増やし、苦手タスクを10%外注する」といった具体的な目標を立てるのも良いでしょう。
継続的な学習とキャリア適応
ADHDの方は、興味の対象が移り変わりやすい傾向があるため、一つの仕事に長く留まることだけが成功ではありません。生涯学習の視点を持ち、新しいスキルを習得したり、興味の変化に合わせてキャリアを柔軟に見直したりすることも大切です。転職を繰り返す場合でも、その原因を分析し、次に活かすことで、より自分に合った働き方を見つけることができます。
自己診断ワーク(時間があるときに)
自分自身をより深く理解するために、以下のようなワークに取り組んでみるのもおすすめです。
興味ゾーンの特定として、RIASEC(現実的、研究的、芸術的、 sociais、企業的、慣習的)といった職業興味検査の無料診断などを活用し、自分の興味がどの領域にあるのか上位2つ程度を把握します。
強みの証拠集めとして、過去に「時間を忘れて夢中になれた」作業や活動を10件程度リストアップし、それらに共通する要素(例:創造性を活かせた、人と深く関われた、問題を解決できたなど)を見つけ出します。
環境チェックとして、現在の職場や過去の職場環境について、「刺激の多さ」「自己裁量の度合い」「サポート体制の手厚さ」などを3段階(高・中・低など)で評価してみます。評価が低い項目は、今後の仕事選びや転職活動における重要な交渉ポイントになります。
これからの一歩
この記事を読んで、ADHDの特性を活かした働き方について少しでも具体的なイメージが湧いたでしょうか。次の一歩として、以下のような行動を考えてみるのも良いでしょう。
興味のある職業クラスターで、**スキルを証明できるもの(ポートフォリオ、GitHubアカウント、資格など)**を作成・準備します。
自分に必要な「合理的配慮リスト」をA4一枚程度にまとめ、面接時の相談材料として準備しておきます。
就労移行支援事業所や発達障害に詳しいオンラインコーチなどを見つけ、定期的に(例:月一回)キャリアレビューや相談の機会を設定します。
もし、あなたがADHDの特性を活かしたキャリアを築きたい、特にIT分野での専門スキルを身につけて活躍したいとお考えなら、チームシャイニーのようなIT特化型の就労移行支援事業所の活用を検討してみてはいかがでしょうか。専門的な知識やスキルを習得し、あなたの強みを最大限に活かせる道が開けるかもしれません。
チームシャイニーでの私の体験談
チームシャイニーのマーケティングゼミに参加しました!注意散漫になりがちで、一つのことに集中するのが苦手な私でも、マーケティングの奥深さにどハマりしています。
最初は難しそうだと思っていたけれど、「どうすれば相手に喜んでもらえるか?」をみんなで考えるのが本当に面白かったんです。講義だけでなく、グループワークでアイデアを出し合ううちに、あっという間に時間が過ぎました。飽きっぽさを忘れられるくらい、新しい刺激に満ちていました。
マーケティングって、商品を売るためのテクニックだと思っていたけど、実は「相手の気持ちを想像すること」だと気づきました。ゼミに参加して、毎日の景色が違って見えるようになり、もっと深く知りたいと思いました!
ADHD向いている仕事よくある質問
まとめ:ADHD向いている仕事一覧:あなたの過集中を開花
ADHDの特性を活かした仕事探しは、決して簡単な道のりではないかもしれません。しかし、自分自身の特性を深く理解し、強みを最大限に活かせる環境を選ぶことで、必ず道は開けます。この記事で紹介した仕事一覧や仕事選びのポイント、職場での工夫、そして利用できる支援制度が、あなたのキャリアを切り拓くための一助となれば幸いです。
特に、変化の速いIT分野は、ADHDの特性である「過集中」や「創造性」、「行動力」を活かせる可能性に満ちています。
もしあなたがIT業界に興味があり、専門的なスキルを身につけて新しいキャリアに挑戦したいと考えているなら、チームシャイニーのようなIT特化型の就労移行支援事業所が力強い味方になるでしょう。
チームシャイニーでは、プログラミング未経験からでもAIエンジニアやデータサイエンティストといった専門職を目指せるカリキュラムを提供し、あなたの「好き」や「得意」を仕事にするためのサポートを行っています。一度、公式サイトをご覧になったり、相談してみたりしてはいかがでしょうか。あなたらしい輝ける場所が、きっと見つかるはずです。



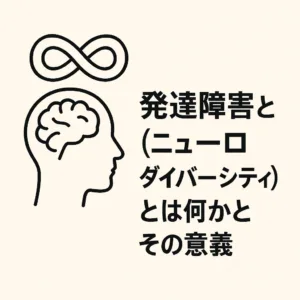
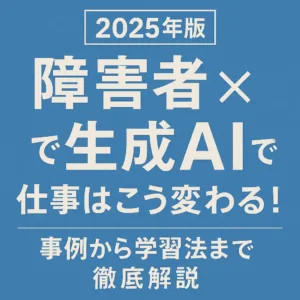
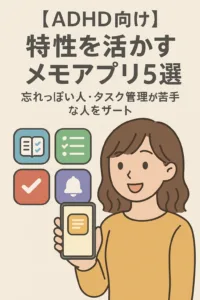
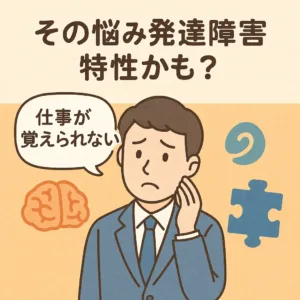
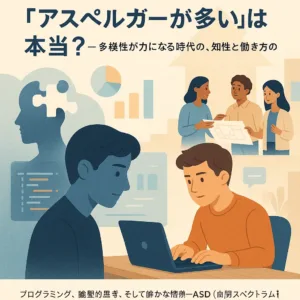


コメント