「ニューロダイバーシティ」という言葉をご存知ですか?これは、発達障害を含む一人ひとりの脳や神経の違いを、治療すべき「欠点」ではなく、尊重すべき「個性」や「強み」として捉えようという考え方です。
少子高齢化が進む現代の日本企業にとって、多様な人材の活躍は、組織の成長に欠かせない重要なテーマとなっています。この記事では、発達障害のある方がその能力を最大限に発揮できる職場環境とはどのようなものか、そしてニューロダイバーシティの視点を取り入れることが、いかにして組織全体の活力と創造性を高めることにつながるのかを、具体的な事例と共に探っていきます。
発達障害とニューロダイバーシティの基本的な考え方
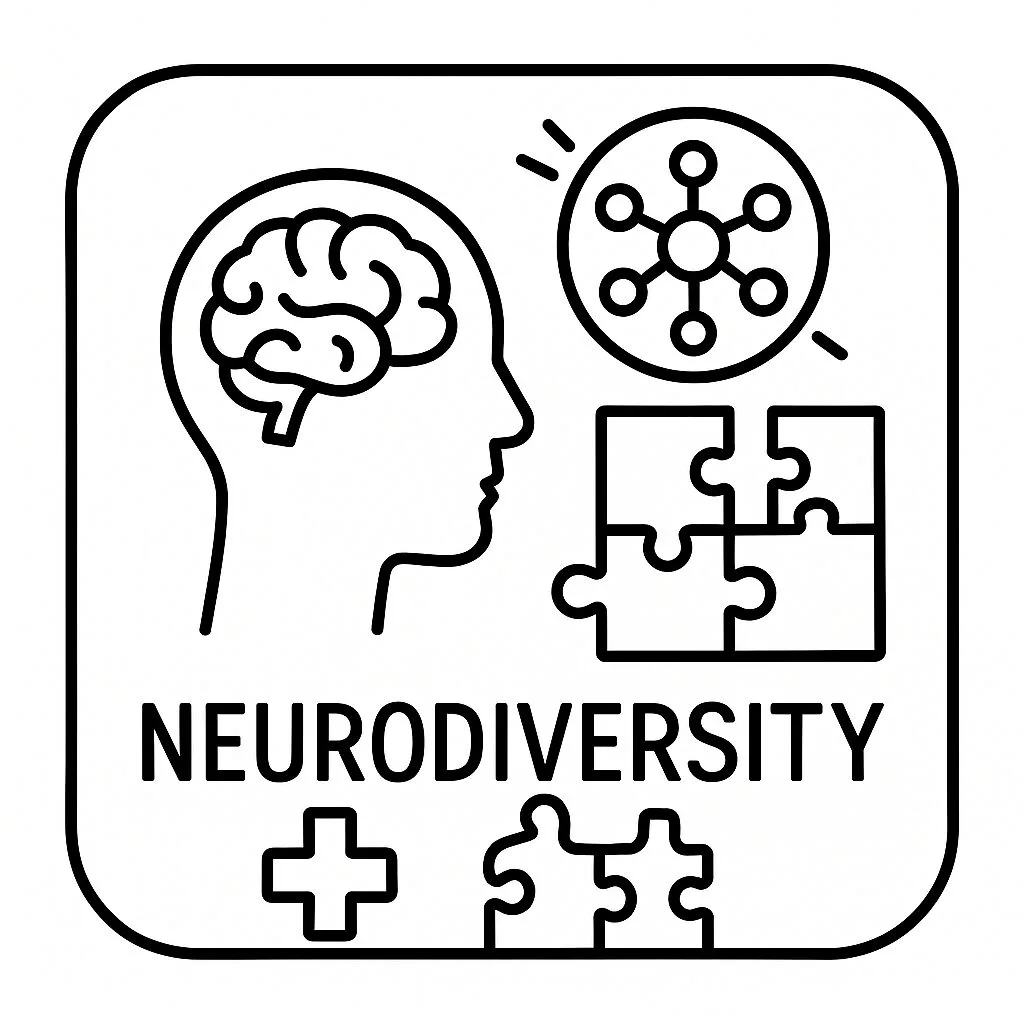
ニューロダイバーシティの定義:発達障害を「違い」として捉える
ニューロダイバーシティ(Neurodiversity)とは、脳や神経の発達における人それぞれの違いを多様性として尊重しようという考え方です。
自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠如・多動症(ADHD)、学習障害(LD)といった発達障害も、能力の優劣ではなく「人間の遺伝子に見られる自然な変異」だと捉え、個性として活かそうとする概念です。
この用語は1990年代にオーストラリアの社会学者ジュディ・シンガー氏が提唱したもので、日本語では「神経多様性」と訳されます。
なぜ今、発達障害の文脈でニューロダイバーシティが重要なのか
ニューロダイバーシティの意義は、発達障害の特性を欠点ではなく強みとして活かし、社会や職場で能力を発揮してもらう点にあります。
1990年代の提唱以来、この概念は主にIT・デジタル分野で推進されてきました。
高度な集中力や創造的思考力など、発達障害のある人が示す特性はイノベーションの源泉になり得るためです。
また、日本のように少子高齢化で労働人口が減少する社会では、多様な人材の活躍促進は企業競争力の強化にも不可欠であり、ニューロダイバーシティへの取り組みは成長戦略としても注目されています。
事実、経済産業省も発達障害の特性を企業の戦力として活かす取り組みを推進しており、これを通じて企業の生産性向上やイノベーション創出を図ろうとしています。要するに、ニューロダイバーシティは「障害者支援」の枠を超え、すべての人が自分の強みを活かせる職場作りを目指す考え方だといえるでしょう。
ニューロダイバーシティと発達障害:企業の採用・定着支援の好事例

ニューロダイバーシティの考え方を採用活動や人材活用に取り入れる企業が増えています。特にIT・Web業界やクリエイティブ職種では、発達障害のある人材の強みを評価し、戦力化する動きが顕著です。ここでは海外・国内それぞれの好事例を紹介します。
海外企業の取り組み
マイクロソフト(Microsoft)
米国のソフトウェア大手マイクロソフトは2015年に「自閉症雇用プログラム(Autism Hiring Program)」を開始しました。
従来の面接重視の採用とは異なり、複数日にわたる作業テストやチームプロジェクトでスキルや適性を多面的に評価する採用プロセスを導入しています。
このプログラム開始から5年間で、デジタル分野の専門課程を修めた170名のニューロダイバース人材を雇用し、その中から主要製品のエンジニアとして活躍する人材も生まれています。一般的な面接では見落とされがちな才能を発掘し、活躍に結びつけた好例と言えます。
グーグル(Google)
インターネットサービス大手のグーグルでは、2021年より「自閉症キャリアプログラム」を開始しました。採用にあたっては事前に質問内容を共有したり、面接時間を延長したり、筆記による面接形式を取り入れるなど、候補者が実力を発揮しやすいよう合理的配慮を行っています。
また、管理職や面接官を含む500人以上の社員に対しトレーニングを実施し、ニューロダイバースな人材を受け入れる職場環境づくりにも力を入れています。採用過程と職場双方で配慮と啓発を徹底することで、人材定着と活躍につなげた事例です。
国内企業の取り組み
オムロン株式会社
制御機器などを手掛けるオムロンは、2021年から「異能人財採用プロジェクト」を開始し、AIや機械学習分野に卓越した能力を持つ発達障害の人材を積極採用しています。
このプロジェクトでは通常の面接よりもインターンシップでの技術力評価を重視し、実務を通じて適性を見る採用方法を取っています。結果、期待以上の成果を出す人材の採用に成功しただけでなく、それを機に管理手法の見直しや職場環境全体の改善にもつながったといいます。発達障害者の活躍が組織改革のきっかけにもなった好例です。
水ing株式会社(スイング)
水インフラ事業の水ingは、経済産業省の「ニューロダイバーシティ導入効果検証調査事業」(2022年度)に協力し、社内で発達障害者の活躍機会拡大に取り組みました。
具体的には、当事者との対話を通じて業務の棚卸しや手順の見直しを行い、仕事を整理・可視化することで効率性向上を図りました。その結果、受け入れ部署(デジタル関連部門)から「業務フロー改善が全体にもプラスになった」といったポジティブな反響が得られています。当事者の視点を取り入れることで組織全体の生産性改善につなげた例です。
アクセンチュア
グローバルコンサルティング企業のアクセンチュア日本法人は、NPO法人Kaienと協働し、精神・発達障がい者が強みを活かして働くための専用オフィス(サテライトオフィス)を開設しています。
2019年に横浜、2020年に東京(立川)、2023年には大阪にも拠点を設立し、多様な業務を用意して多数の発達障害のある社員を受け入れています。各拠点では職務指導員によるきめ細かな育成支援と、働きやすい環境整備により高い定着率を実現しており、社内から「事業に貢献する組織」と期待を寄せられるまでに成長しています。
培ったノウハウを社会に還元すべく、さらなる拠点拡大とニューロダイバーシティ推進に取り組んでいる点も注目されます。
発達障害とニューロダイバーシティ:職場でできる支援と配慮

採用後、発達障害のある社員が能力を発揮し長く働けるようにするには、職場での支援や配慮が欠かせません。ここでは具体的な配慮のポイントをいくつか紹介します。
発達障害の特性を活かす柔軟な働き方
多様な働き方を可能にする制度整備は、ニューロダイバーシティ推進の鍵の一つです。
例えば、定時の出退勤が苦手な社員にはフレックスタイム制で始業・終業時刻を本人が決められるようにしたり、1日8時間勤務が精神的に負担となる場合には時短勤務を認めるといった配慮が有効です。
リモートワーク(在宅勤務)も近年増えており、周囲の刺激を減らしやすいメリットがある一方、コミュニケーション機会の減少による孤立などの注意点もあります。企業側は在宅勤務希望者に対し、業務目標の明確化や定期的なオンライン面談によるサポートを行い、必要に応じて出社と在宅を組み合わせる(ハイブリッド勤務)など柔軟に運用することが望ましいでしょう。
発達障害の特性「過集中」への対処法
発達障害のある人の中には、一度興味のあることに没頭すると驚異的な集中力を発揮する一方で、周囲が見えなくなる「過集中(ハイパーフォーカス)」の傾向を持つ人がいます。
これは優れた強みである一方、休憩を忘れて働き続け、後に極度の疲労に陥るなどの健康面のリスクや、周囲との摩擦を生む可能性があります。対策としては、本人が定期的にアラームを鳴らして休憩を取ったり、周囲が適宜声がけをしたりするなど、脳をクールダウンする仕組みを用意することが有効です。
発達障害のある社員へのコミュニケーションと環境配慮
発達障害の特性上、口頭の曖昧な指示では理解が難しい場合があるため、指示は明確な文章やチェックリストで渡す、タスクの優先順位を見える化するなど、わかりやすさを重視した伝え方が効果的です。
また、作業環境については、静かな集中スペースを用意する、光や音の刺激が強すぎないレイアウトにする、イヤーマフの使用を許可するといった配慮が考えられます。大切なのは、「何に困り、どんな配慮があれば能力を発揮できるか」を本人と話し合い、ケースバイケースで柔軟に対応することです。
発達障害当事者の声から学ぶニューロダイバーシティ
実際に働いている発達障害当事者の声から、職場でどのような配慮が喜ばれているか、またどんな改善が望まれているかを見てみましょう。
「受け入れられている」と感じられることの大切さ
採用時から職場の受容的な態度を示すことが、その人のポテンシャルを引き出す第一歩になります。ある当事者は、面接官の温かい雰囲気が入社の決め手になったと語っています。入社後も、自分のペースで業務を始めさせてもらい、徐々に成長できたことで自信がついたそうです。
職場で配慮されて嬉しかったことと、改善が望まれる課題
「ミスしても頭ごなしに怒られずフォローしてもらえた」「困ったとき相談できる先輩がいる」など、職場からの思いやりや環境調整が大きな助けになるという声が多く聞かれます。一方で、「『あいつは発達障害だ』とレッテルを貼る人がいる」など、無理解や偏見が当事者の働きづらさを助長している現状も指摘されています。企業は社員教育や啓発活動を通じて障害理解を深め、心理的安全性の高い職場風土を醸成することが求められます。
まとめ:発達障害とニューロダイバーシティを活かし、多様な「脳」が輝く職場へ
ニューロダイバーシティとは、発達障害を含む神経発達の多様性を個性・強みとして肯定し、社会で活かすという視点です。企業がこの考え方を取り入れ、評価方法の工夫や受け入れ体制の整備、柔軟な働き方や個々の特性に応じた配慮を行うことで、当事者が活躍できるだけでなく、組織全体の活力と創造性を高めることにつながります。
「100通りの脳」がそれぞれ輝ける職場を作るために、まずは先入観を捨てて本人の話に耳を傾け、小さな配慮を積み重ねることが重要です。多様な人材がお互いを尊重し合い、それぞれの強みを発揮できる環境を築くことで、企業も成長し続けるという好循環を生み出しましょう。
参考文献・情報ソース:
- 経済産業省「ニューロダイバーシティの推進について」(定義と国内の取り組み)meti.go.jpmeti.go.jp
- 朝日新聞SDGs記事「ニューロダイバーシティとは? 発達障害との関係や具体例」(企業事例や推進方法)asahi.comasahi.comasahi.comasahi.comasahi.com
- 電通報「『100通りの脳』は、日本の働く場をどのように変えるのか」(ニューロダイバーシティ概説)dentsu-ho.com
- Yahoo!ニュース オリジナル特集「大人の発達障害、当事者が直面する就労の困難」(合理的配慮不足や偏見の事例)sdgs.yahoo.co.jpsdgs.yahoo.co.jp
- 札幌市障がい者就労事例集(当事者の職場経験談とメッセージ)city.sapporo.jpcity.sapporo.jp

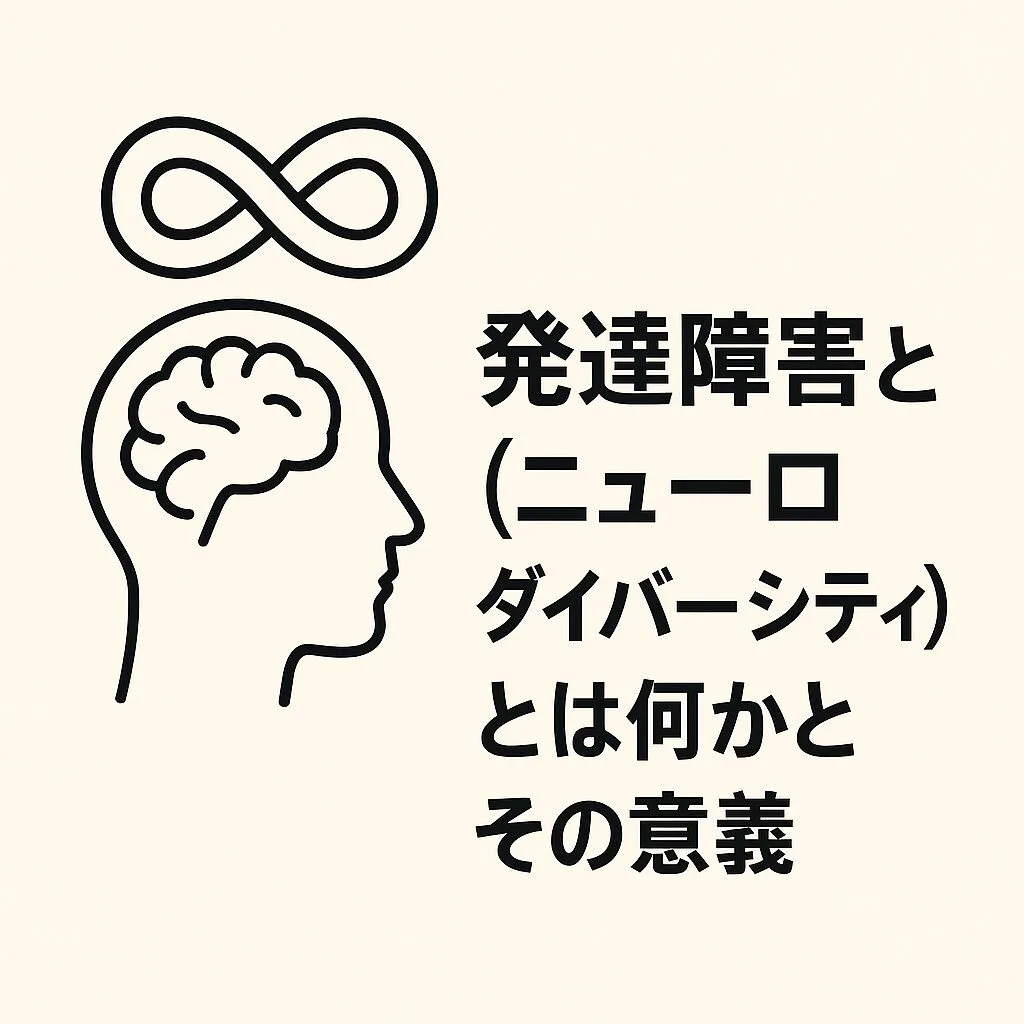

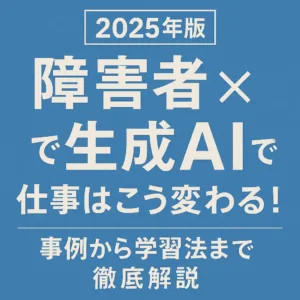
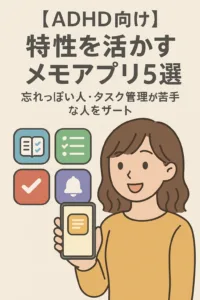

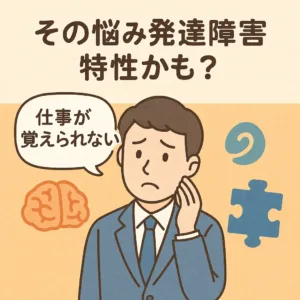
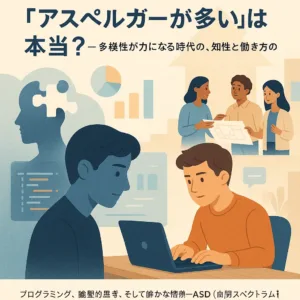


コメント