「発達障害だからエンジニアは向いていない?」そんな不安を抱えていませんか。
この記事では、発達障害の特性とエンジニア職(PG/SE)の適性について、よくある誤解から具体的な困難、そして活かせる強みまで多角的に解説します。環境や合理的配慮の重要性、さらに先端IT特化型就労移行支援「チームシャイニー」のようなサポート体制についても詳しくご紹介。
あなたらしいキャリアを見つけるための一歩を踏み出しましょう。
「発達障害だからエンジニアは向いていない」は本当?

「発達障害 エンジニア 向いてない」と検索されたあなたは、ご自身や身近な方の発達障害(ASD、ADHD、LDなど)とITエンジニアという職業の適性について、疑問や不安をお持ちかもしれません。あるいは、エンジニアを目指す中で、本当に自分に合っているのか情報を集めている最中かもしれませんね。
インターネット上には、「発達障害の特性はエンジニアに向いている」という意見も、「コミュニケーションが重要だから難しい」という意見も存在します。一体、どちらが真実なのでしょうか?
結論から言えば、「発達障害だからエンジニアに向いている・向いていない」と一概に断定することはできません。個人の持つ多様な特性、エンジニアという仕事の幅広さ、そして働く環境という3つの要素が複雑に絡み合っているためです。
なぜ「向いていない」と感じてしまうのか? – 不安の背景にある要因
「向いていない」と感じる背景には、発達障害の一般的な特性とエンジニア業務の特定の側面を結びつけた見方があります。
コミュニケーションへの懸念
チームでの開発作業には、メンバー間の連携が不可欠です。ASD(自閉スペクトラム症)の方に見られる曖昧な表現の理解の難しさや、非言語的な意図の読み取りにくさが、チームワークの障壁になると考えられることがあります。また、ADHD(注意欠如・多動症)の方の場合、相手の話を最後まで聞くことや、会話のテンポを合わせることへの難しさが指摘されることもあります。(参考:リサーチ結果内の複数ソース)
タスク管理・遂行への不安
納期管理や複数の業務を同時に進めるマルチタスクは、エンジニア業務でしばしば求められます。ADHDの方に見られる計画性の苦手さや注意散漫さが、業務遂行の妨げになると考えられることがあります。
環境への適応の難しさ
オフィスの騒音や照明など、感覚過敏がある方にとっては集中を妨げる要因が多い環境もあります。また、ASDの方に見られる変化への抵抗感が、変化の速いIT業界では不利になると見なされることもあります。
しかし、これらはあくまで一面的な見方であり、発達障害の特性の現れ方は人それぞれです。また、エンジニアの仕事内容も、常に高いコミュニケーション能力やマルチタスク能力が求められるわけではありません。
実は誤解? 発達障害でのエンジニア職種の多様性

「エンジニア」と一言で言っても、その役割は多岐にわたります。特に、**プログラマー(PG)とシステムエンジニア(SE)**では、求められるスキルや働き方が大きく異なります。この違いを理解することが、適性を考える上で非常に重要です。
| 役割 | 主な業務内容 | 求められる主なスキル |
|---|---|---|
| プログラマー (PG) | SEが作成した設計書に基づき、プログラミング言語を用いてコードを書き、システムやソフトウェアを実装する。 | プログラミングスキル、仕様理解力、(比較的)高い集中力 |
| システムエンジニア (SE) | 顧客から要望を聞き取り(ヒアリング)、システムの設計、プロジェクト全体の進捗管理、チーム調整など。 | 技術力、コミュニケーション能力、調整能力、マネジメント能力 |
一般的に、PGは発達障害の特性を持つ方に向いている可能性が高いと言われることがあります。
なぜなら、論理的に物事を考える力や、一度集中すると深く没頭できる力(過集中)といった強みを活かしやすく、SEに比べて対人折衝の場面が少ない傾向があるためです。
一方で、SEは顧客との曖昧なやり取りや多くの人との調整が必要なため、コミュニケーションに苦手意識がある方にとっては困難を感じやすい職種とされています。
ただし、これもあくまで一般的な傾向です。PGでもチームでの連携は必要ですし、SEの業務の中でも特定の分野(例えばインフラ構築など)では、コミュニケーションよりも専門技術が重視される場合もあります。大切なのは、「PGかSEか」という肩書きだけでなく、具体的な業務内容や求められるスキルが自分の特性に合っているかを見極めることです。
発達障害の「強み」がエンジニア職で活きる可能性 – 論理思考、集中力、創造性
発達障害の特性は、困難さだけでなく、エンジニアリング分野で大きな「強み」となり得ます。
- 強い集中力(過集中): 興味を持った特定の技術や課題に対して、驚くほどの集中力を発揮し、深く掘り下げることができます。複雑なバグの原因究明や、難易度の高いプログラミングにおいて大きな武器となります。(参考:リサーチ結果内の複数ソース)
- 論理的・分析的思考: ルールや構造に基づいて物事を捉え、論理的に考える力は、プログラミングの根幹をなすアルゴリズムの理解や設計、システム全体の構造把握、データ分析などに非常に役立ちます。(参考:リサーチ結果内の複数ソース)
- 細部への注意力と正確性: 他の人が見逃しがちな細かなエラーや矛盾点に気づく力は、コードの品質を高めるデバッグ作業やテスト工程で非常に重要です。
- 創造性と革新的思考: 既存の枠にとらわれないユニークな視点や発想力(特にADHDの方に見られる傾向)は、新しい技術の開発や問題解決において、革新的なアイデアを生み出すきっかけになります。
- パターン認識能力: 膨大な情報の中から規則性や関連性を見つけ出す能力は、データ分析やシステム設計、複雑なコードの理解などに活かせます。
実際に、世界的なIT企業が集まるシリコンバレーでは、発達障害の傾向を持つエンジニアが多く活躍していると言われ、「シリコンバレー症候群」という言葉もあるほどです。(参考: Neuro-diversityAtgp)これは、彼らの持つ特性がIT分野で高く評価されている証拠と言えるでしょう。
重要なのは、「困難さ」と「強み」は表裏一体である場合が多いということです。例えば、「過集中」は強みですが、他のタスクへの切り替えが苦手という側面もあります。これらの特性がどちらに働くかは、**仕事内容や環境との相性(マッチング)次第なのです。
発達障害でエンジニアとして働く上で直面しやすい困難とその対策
発達障害の特性を持つ方がエンジニアとして働く上で、具体的にどのような困難に直面しやすいのでしょうか。また、それらにどう対処していけば良いのでしょうか。実体験や専門家の意見を基に見ていきましょう。
コミュニケーションの壁
曖昧さの理解
「いい感じに」「なるべく早く」といった曖昧な指示や、冗談、皮肉などの言葉通りの意味ではない表現の理解が難しい場合があります。これが原因で、指示された内容と違う成果物になってしまったり、認識のずれが生じたりすることがあります。
- 対策: 指示を受ける際に、「〇〇ということですね?」「具体的には△△すればよろしいでしょうか?」と確認する、指示内容をメールなどテキストで送ってもらうよう依頼する、などが有効です。(参考:実体験談)
非言語サインの読み取り
表情や声のトーンから相手の感情や意図を察するのが苦手な場合、場の空気を読んだり、相手の状況に合わせた対応が難しかったりすることがあります。
- 対策: 無理に空気を読もうとするより、不明な点は「今、〇〇について確認してもよろしいでしょうか?」のように、言葉で確認する習慣をつけることが大切です。テキストベース(チャットなど)でのコミュニケーションを増やすのも有効な場合があります。
チームワーク
チームメンバーとの認識合わせや、暗黙の了解、非公式なルールへの対応に戸惑うことがあります。
- 対策: チームのルールや進め方について、不明な点は積極的に質問する。自分の考えを伝える際は、事前にメモにまとめてから話すなどの工夫が役立ちます。
タスク管理と実行機能
集中と注意
興味のないタスクへの集中維持が難しかったり(ADHD)、逆に一つのことに集中しすぎて他のことが見えなくなったり(過集中:ASD/ADHD)することがあります。
- 対策: タイマーを使って作業時間を区切る(ポモドーロテクニックなど)、集中が途切れたら短時間の休憩を挟む、興味のある分野やタスクから取り組む、などが考えられます。過集中に対しては、意識的に休憩時間を設定することが重要です。
計画と優先順位付け
タスクの所要時間を見積もったり、優先順位をつけて計画的に進めたり、複数のタスクを同時に管理したりするのが苦手な場合があります。
エンジニアでも発達障害の働き方を見つける – 環境と合理的配慮の重要性

発達障害のある方がエンジニアとして能力を発揮し、長く働き続けるためには、仕事内容そのものだけでなく、働く環境が非常に重要です。「どの仕事をするか」と同じくらい、あるいはそれ以上に、**「どこで、誰と、どのように働くか」**が鍵となります。
「仕事内容」だけでなく「職場環境」がカギ – リモートワーク、静かなオフィス
たとえ仕事内容が自分の得意なことであっても、職場環境が合わなければ、能力を発揮できなかったり、心身ともに疲弊してしまったりする可能性があります。
- 物理的な環境: 感覚過敏がある方にとっては、静かで、照明などが調整された環境が望ましいでしょう。個室やパーテーションのある席、あるいはリモートワーク(在宅勤務)は有効な選択肢です。実際に、リモートワークによって人間関係のストレスや集中困難が大幅に軽減されたという当事者の声もあります。(参考:実体験談)
- コミュニケーション文化: 指示が明確で、質問や相談がしやすい雰囲気があるかどうかも重要です。「あれ」「これ」といった曖昧な指示が少なく、具体的な言葉で説明してくれる文化がある職場は働きやすいでしょう。
- 企業文化と理解: 発達障害や多様性に対する理解があり、個々の特性を尊重してくれる企業文化があるかどうかも大切なポイントです。「なんで普通のことができないんだ」といった言葉を受ける環境ではなく、個性を認め合い、サポートし合える環境が理想です。(参考:実体験談)
合理的配慮とは? – 具体的な配慮例
企業には、障害のある従業員が能力を発揮できるよう、合理的配慮を提供することが法律で義務付けられています(障害者差別解消法、障害者雇用促進法)。これは、個々の困難を取り除くための調整であり、本人の申し出に基づき、企業にとって過重な負担にならない範囲で行われます。
エンジニア職における具体的な配慮例としては、以下のようなものが考えられます。
- 対策: タスク管理ツール(Trello, Asana, Microsoft ToDoなど)やカレンダーアプリを活用する。上司や同僚に相談し、タスクの優先順位付けやスケジューリングを手伝ってもらう。一つのタスクが終わってから次の指示をもらう(シングルタスク)よう依頼する。
感覚過敏と職場環境 – 音、光、オープンスペース
- 環境刺激: オフィスの話し声、キーボードの音、蛍光灯のちらつき、空調の音、特定の匂いなどが、集中を妨げたり、強いストレスになったりすることがあります。特にオープンスペースのオフィスは刺激が多い場合があります。
- 対策: ノイズキャンセリング機能付きのイヤホンや耳栓の使用許可を得る、パーテーションで区切られた席や個室を利用する、照明を調整する、可能であればリモートワーク(在宅勤務)を選択する、といった環境調整が有効です。
変化への適応 – ルーティンと柔軟性
- 予期せぬ変更: 急な仕様変更やスケジュールの変更、手順の変更など、予期せぬ変化に対して強いストレスを感じ、適応に時間がかかることがあります(特にASDの方)。
- 対策: 可能な限り、変更がある場合は事前に通知してもらうよう依頼する。変更内容や理由を具体的に説明してもらう。手順が明確なマニュアルを作成・活用する。
困難を乗り越える工夫 – メモ、ツール活用、自己理解
これらの困難は、個人の努力だけで解決できるものではありません。しかし、当事者自身ができる工夫も多くあります。会議や会話の内容を積極的にメモする、タスク管理ツールやリマインダーを活用する、自分の苦手なことや必要な配慮を周囲に伝えること(自己理解とセルフ・アドボカシー)などが、困難を軽減するために役立ちます。
大切なのは、「できないこと」に焦点を当てるのではなく、**「どうすればできるようになるか」「どのようなサポートがあれば力を発揮できるか」**という視点で考えることです。
エンジニアでも発達障害で働き方を見つける

発達障害のある方がエンジニアとして能力を発揮し、長く働き続けるためには、仕事内容そのものだけでなく、働く環境が非常に重要です。「どの仕事をするか」と同じくらい、あるいはそれ以上に、**「どこで、誰と、どのように働くか」**が鍵となります。(参考: Cocopia-career + 2)
「仕事内容」だけでなく「職場環境」がカギ – リモートワーク、静かなオフィス
たとえ仕事内容が自分の得意なことであっても、職場環境が合わなければ、能力を発揮できなかったり、心身ともに疲弊してしまったりする可能性があります。
- 物理的な環境: 感覚過敏がある方にとっては、静かで、照明などが調整された環境が望ましいでしょう。個室やパーテーションのある席、あるいはリモートワーク(在宅勤務)は有効な選択肢です。実際に、リモートワークによって人間関係のストレスや集中困難が大幅に軽減されたという当事者の声もあります。(参考:実体験談)
- コミュニケーション文化: 指示が明確で、質問や相談がしやすい雰囲気があるかどうかも重要です。「あれ」「これ」といった曖昧な指示が少なく、具体的な言葉で説明してくれる文化がある職場は働きやすいでしょう。
- 企業文化と理解: 発達障害や多様性に対する理解があり、個々の特性を尊重してくれる企業文化があるかどうかも大切なポイントです。「なんで普通のことができないんだ」といった言葉を受ける環境ではなく、個性を認め合い、サポートし合える環境が理想です。
合理的配慮とは? – 具体的な配慮例
企業には、障害のある従業員が能力を発揮できるよう、合理的配慮を提供することが法律で義務付けられています(障害者差別解消法、障害者雇用促進法)。これは、個々の困難を取り除くための調整であり、本人の申し出に基づき、企業にとって過重な負担にならない範囲で行われます。
エンジニア職における具体的な配慮例としては、以下のようなものが考えられます。
困難を乗り越える工夫 – メモ、ツール活用、自己理解
これらの困難は、個人の努力だけで解決できるものではありません。しかし、当事者自身ができる工夫も多くあります。会議や会話の内容を積極的にメモする、タスク管理ツールやリマインダーを活用する、自分の苦手なことや必要な配慮を周囲に伝えること(自己理解とセルフ・アドボカシー)などが、困難を軽減するために役立ちます。
大切なのは、「できないこと」に焦点を当てるのではなく、**「どうすればできるようになるか」「どのようなサポートがあれば力を発揮できるか」**という視点で考えることです。
企業側の変化 – ニューロダイバーシティ採用の動き
近年、特にIT業界を中心に、発達障害を含む多様な神経特性を持つ人々を積極的に受け入れ、その能力を活かそうとする**「ニューロダイバーシティ」**の考え方が広がっています。
SAP社の「Autism at Work」やマイクロソフト社の「Neurodiversity Hiring Program」など、海外の先進企業では、発達障害のある人材を専門的に採用・育成するプログラムが導入されています。(参考: SAP, Microsoft Careers)これらの企業は、発達障害のある人が持つ独自の視点や才能が、組織のイノベーションや競争力向上に貢献すると認識しているのです。
日本国内でも、ニューロダイバーシティ採用に取り組む企業や、発達障害のある人のIT分野での活躍を支援する動きが出てきています。(参考:ダイヤモンド・オンライン)これは、単に「障害者雇用」という枠組みを超え、多様な人材を企業の成長に不可欠な「資産」として捉える、前向きな変化と言えるでしょう。
自分に必要な配慮を伝えるには? – 自己理解とセルフ・アドボカシー
合理的配慮を受けるためには、まず自分自身が**「どのようなことに困難を感じ、どのような配慮があれば働きやすくなるのか」**を理解し、それを企業側に適切に伝えること(セルフ・アドボカシー)が重要です。
自分の特性を客観的に把握するためには、専門機関(発達障害者支援センター、医療機関など)に相談したり、過去の経験を振り返ったりすることが役立ちます。そして、面接時や入社後に、具体的な困りごとと希望する配慮内容を、理由とともに説明できるように準備しておきましょう。
ITエンジニアへの挑戦をサポート – 就労移行支援という選択肢

「エンジニアに興味はあるけれど、スキルに自信がない」「自分に合う職場を見つけられるか不安」「必要な配慮をどう伝えればいいかわからない」… このような悩みを抱えている方にとって、就労移行支援は心強い味方となります。
就労移行支援とは? – スキル習得から就職・定着まで
就労移行支援は、障害のある方が一般企業への就職を目指すための、国が定める障害福祉サービスの一つです。原則として最長2年間、以下のようなサポートを(多くの場合、自己負担なく)受けることができます。
- 職業訓練: ビジネスマナー、コミュニケーションスキル、PCスキルなど、働く上で必要な基礎的なスキルを学びます。
- 専門スキルの習得: プログラミング、Webデザイン、データ分析など、希望する職種に応じた専門スキルを習得できるプログラムもあります。
- 自己理解の促進: 自身の障害特性や得意・不得意を理解し、対処法を学びます。
- 職場探しと就職活動支援: 求人情報の提供、応募書類の作成サポート、面接練習などを行います。企業へのインターンシップ(職場実習)の機会もあります。
- 職場定着支援: 就職後も、安定して働き続けられるように、職場との間に入って環境調整を行ったり、定期的な面談で相談に乗ったりします。
発達障害に特化した支援のメリット
就労移行支援事業所の中には、発達障害のある方の支援に特化したところも増えています。こうした事業所では、発達障害の特性を深く理解したスタッフが、一人ひとりのペースや認知特性に合わせた個別支援計画を作成し、きめ細やかなサポートを提供してくれます。
ITスキル特化型の就労移行支援が増加中
近年、IT人材の需要増加に伴い、プログラミングやWebデザイン、データサイエンスといったITスキルに特化したカリキュラムを提供する就労移行支援事業所も増えています。未経験からでも、実践的なITスキルを学び、エンジニアとしての就職を目指すことが可能です。
【注目】先端IT特化型就労移行支援「チームシャイニー」とは?
数ある就労移行支援事業所の中でも、特にAI(人工知能)やデータサイエンスといった先端IT分野に特化し、発達障害のある方のエンジニア就職を強力にサポートしているのが、東京・秋葉原にある**「チームシャイニー」**です。
もしあなたが、「プログラミングだけでなく、もっと専門的なITスキルを身につけたい」「自分の特性を本当に理解してくれる環境で学びたい」「将来性のある分野で活躍したい」と考えているなら、チームシャイニーは非常に魅力的な選択肢となるでしょう。
チームシャイニーが選ばれる理由①:AI・データサイエンス特化の本格カリキュラム
チームシャイニーの最大の特徴は、AI(機械学習、深層学習)やデータサイエンスに特化した、非常に専門的で実践的なカリキュラムを提供している点です。PythonやJavaScriptといった基礎的なプログラミングはもちろん、ChatGPTやStable Diffusionなどの生成AI活用、統計学、データ分析ツール(Excel, Tableau, R言語など)まで、段階的に学ぶことができます。(参考: チームシャイニー公式サイト) KaggleやSignateといったデータ分析コンペティションへの参加も推奨しており、実務で通用するスキルとポートフォリオを構築できます。
チームシャイニーが選ばれる理由②:現役エンジニア&当事者スタッフによる共感的サポート
チームシャイニーのスタッフは、全員が現役のITエンジニアであり、かつ発達障害の特性を持つ当事者です。(参考: チームシャイニー公式サイト)これは非常にユニークで、技術的な指導の質の高さはもちろん、「発達障害のある人がITスキルを学ぶ上で、どこでつまずきやすいか」「どのような伝え方なら理解しやすいか」を、自身の経験に基づいて熟知しています。あなたの特性や困りごとに深く共感し、専門知識と当事者視点の両面から、最適なサポートを提供してくれます。Slackでの指示の出し方やタスクの分解方法など、具体的な合理的配慮のノウハウも豊富です。
チームシャイニーが選ばれる理由③:高い技術職就職率(85%)と手厚い定着支援(180日)
チームシャイニーの卒業生の85%が、プログラマーやデータアナリストといった技術職として就職しています。(参考: チームシャイニー公式サイト)これは、専門的なカリキュラムと手厚い就職サポートの質の高さを物語っています。さらに、就職後も最長180日間(約6ヶ月)の定着支援が受けられます。職場との三者面談や、リモートでのフォローアップなどを通じて、あなたが新しい環境に慣れ、安心して働き続けられるよう、長期的にサポートしてくれます。「就職してもすぐに辞めてしまうのでは…」という不安を抱える方にとって、この手厚い定着支援は大きな安心材料となるでしょう。
チームシャイニーが選ばれる理由④:公的機関からの信頼と評価
チームシャイニーは、その先進的な取り組みと実績が公的にも高く評価されています。
- 総務省「異能vation」ネットワーク拠点認定: 独創的な技術やアイデアを持つ人材を発掘・支援する国のプログラムの連携拠点として認定されています。(参考: チームシャイニー公式サイト)
- 東京都ソーシャルファーム認証: 障害のある方などが働きがいを持って活躍できる企業として、東京都から認証を受けています。(参考: ShinyLabサイト)
これらの認定は、チームシャイニーが信頼できる支援機関であり、社会的に価値のある取り組みを行っていることの証です。
費用は? ほとんどの方が自己負担なしで利用可能
就労移行支援は国の制度に基づいているため、利用者の**95%以上が自己負担なし(無料)**でサービスを受けています。(参考: チームシャイニー公式サイト)前年の所得に応じて一部自己負担が発生する場合もありますが、上限額が定められています。交通費の補助制度もありますので、費用面での心配はほとんどありません。
まとめ:発達障害だからエンジニアは向いていない
発達障害とエンジニアの適性は「向いている・いない」で単純に語れるものではありません。大切なのは個々の特性と仕事内容、そして何より職場環境とのマッチングです。論理的思考や集中力は大きな強みになり得ます。適切なサポートや合理的配慮があれば、困難も乗り越えられます。先端IT特化の「チームシャイニー」のような就労移行支援も活用し、あなたに合った道を探求しませんか。まずは無料相談から、可能性を広げましょう。

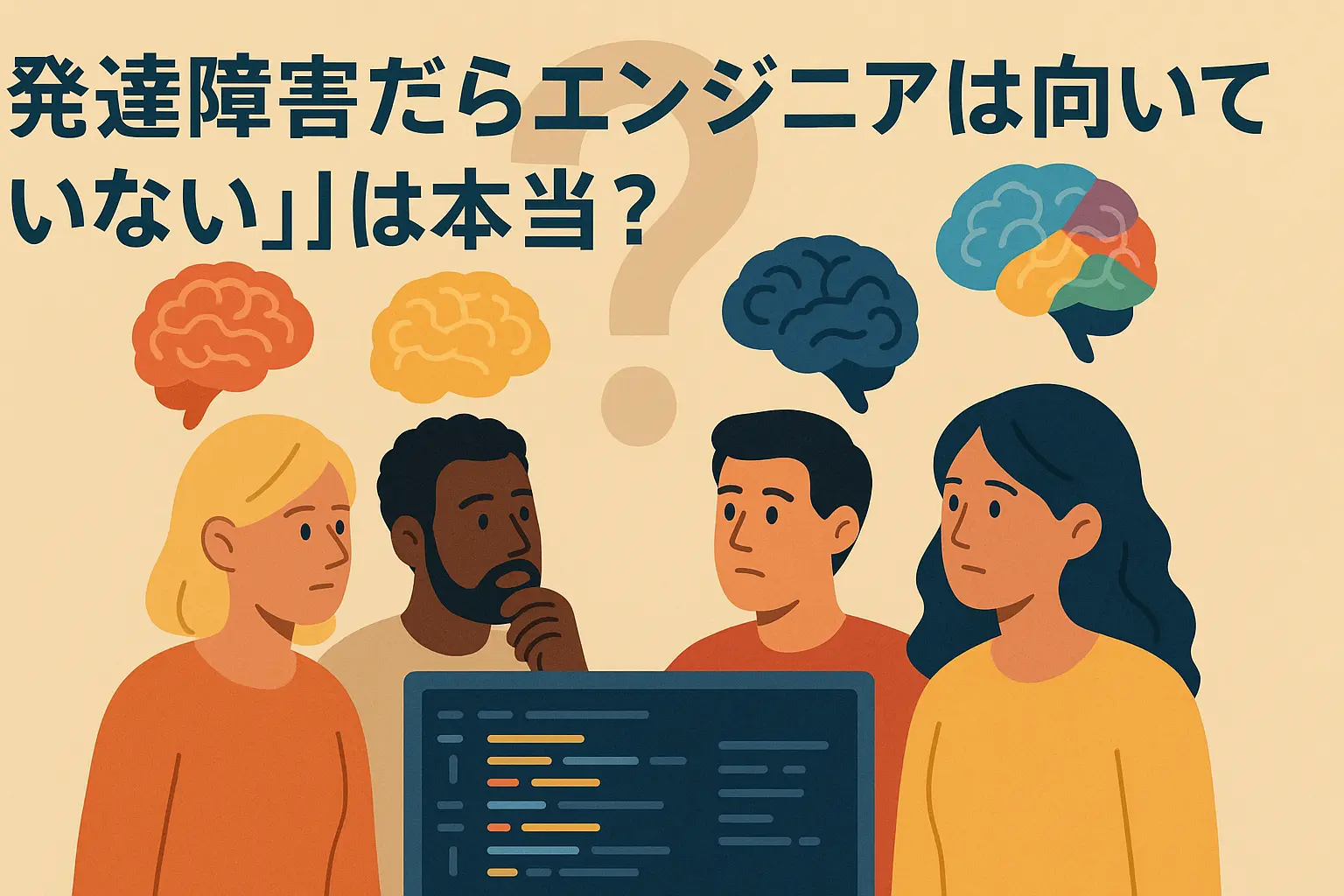

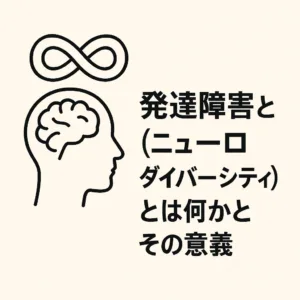
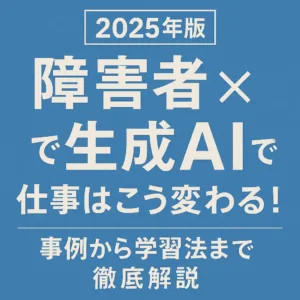
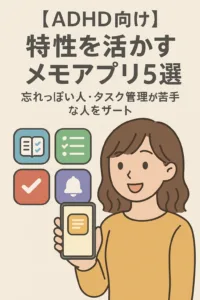

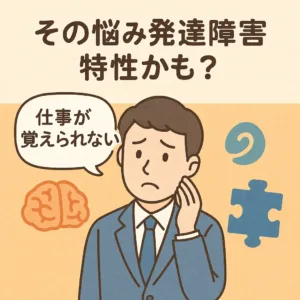
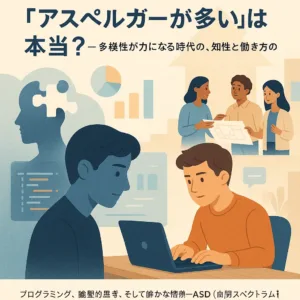

コメント