目次
――制度のしくみ・最新データ・利用開始までのすべて
障害のある方が「一般企業で長く働く」ための公的ステップとして定着した 就労移行支援。この記事では 特定の事業者名を挙げず に、制度の全体像から最新統計、費用、改定トピックスまでを体系的にまとめました。初めて調べる方はもちろん、事業所選びで迷っている方もぜひご活用ください。
1. 就労移行支援とは
障害者総合支援法に基づく就労系障害福祉サービスの一つ。一般就労が見込まれる障害者に対し、就職準備・職業訓練・企業実習・就職活動・定着支援を最長2年間(+延長可)で一体的に提供します。
2. 最新データで見る就労移行支援(2024〜2025年)
| 指標 | 最新値・概要 |
|---|---|
| 全国事業所数 | 3,393 か所(2022年10月調査) |
| 一般就職率 | 57.2 %(2022年就労移行終了者ベース) |
| 就職後3か月定着率 | 90.3 % (2024年調査) |
| 平均利用期間 | 1〜2年がボリュームゾーン(最長2年) |
| 自己負担 | 世帯所得別上限制で多くの利用者が 実質0円。上限額は0/9,300/37,200円の3段階 |
3. 対象者と利用要件
- 18〜64歳で一般就労を希望する障害者(身体・知的・精神・発達・難病等)
- 障害者手帳がなくても、医師の診断書や自治体の判断で利用可能
- 市町村発行の「障害福祉サービス受給者証」が必須
- 最長2年間(状況により延長可)利用でき、途中退所でも残期間は再利用可能
4. 支援内容とプログラムの流れ
| ステージ | 代表的なプログラム例 |
|---|---|
| ① 就職準備 | 生活リズム調整、自己理解、ストレスマネジメント |
| ② スキルトレーニング | Office・IT基礎、コミュニケーション、軽作業、eラーニング |
| ③ 企業実習 | 自社開拓/連携企業でのインターン、適性確認 |
| ④ 就職活動 | 応募書類作成、模擬面接、企業同行 |
| ⑤ 定着支援(最長3年半) | 定期面談、職務調整提案、メンタルフォロー |
5. 費用と助成制度
1割負担が原則ですが、月額負担上限 が所得区分で決まります。
| 世帯所得区分 | 月額上限 | 典型的世帯例 |
|---|---|---|
| 生活保護・非課税 | 0円 | 年金・手当のみ |
| 市町村民税課税 ¹ | 9,300円 | 年収概ね600万円未満 |
| 市町村民税課税 ² | 37,200円 | 年収概ね600万円以上 |
上限を超えたサービス量を利用しても追加請求はありません。交通費や昼食補助は自治体・事業所で独自支給されるケースもあるため要確認です。
6. 利用開始までの5ステップ(標準的な手順)
- 問い合わせ・資料請求
- 見学・無料体験(家族同席OK、複数事業所比較推奨)
- 受給者証申請(自治体窓口で面談、省略可の自治体も)
- 個別支援計画の策定・契約
- 正式利用開始(週1〜5日、半日利用も可)
7. 事業所選び7つのチェックリスト
- 公開している 就職率・定着率
- 実習先企業 の業種・規模の多様性
- IT、クリエイティブ、農業など 専門プログラム の有無
- スタッフ構成(就労支援員・臨床心理士・医療職など)
- オンライン訓練や テレワーク対応 設備
- 事業所の 通いやすさ(立地・開所時間・送迎の有無)
- アセスメントの質(目標設定・進捗レビューが定期か)
8. 2024〜2025年 報酬改定トピックス
- 成果指標(就職率等)の公表義務化 が段階導入へ
- デジタルスキル訓練加算:IT訓練を一定時間以上実施した場合に評価点数アップ
- 遠隔支援(ビデオ面談・オンライン講座)の算定要件明確化
- 企業連携加算の見直し:就職後6か月時点の定着を評価する仕組みに変更
- 支援記録のDX化:電子システム導入で加算対象 など
9. まとめと次の一歩
- 就労移行支援は「就職準備 → 実習 → 就職 → 定着」までを公費で伴走
- 全国3,000か所超、就職率57 %、定着率90 %と成果は着実に向上
- 多くの利用者は自己負担ゼロで利用可能
- まずは 複数事業所を見学し、自分に合うプログラムと支援体制を比較しましょう
行動ヒント
今週中に最寄りの事業所を2〜3か所ピックアップし、オンラインまたは対面での見学予約を入れてみてください。実際の雰囲気を体験することで、自分にとって最適な環境が見えてきます。
本記事は 2025年6月26日時点の公表資料をもとに作成しました。制度や数値は今後変更される可能性があります。必ず最新情報を自治体・事業所へ直接ご確認ください。



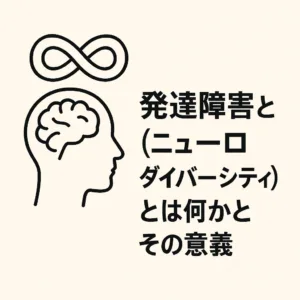
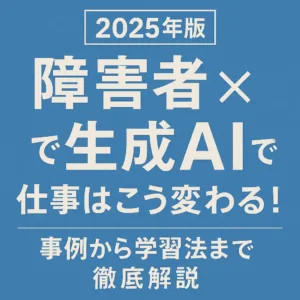
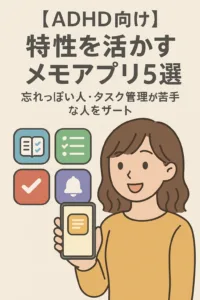

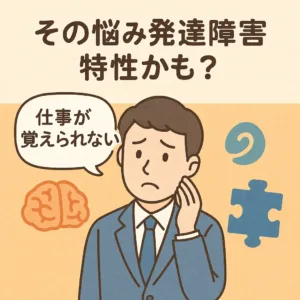
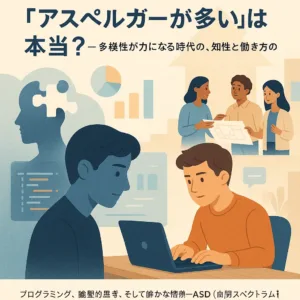

コメント